宅建試験には、2018年に平成最後となった試験で初めて受験し、かろうじてですがそこで合格することができています。
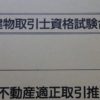
この試験に対しては、テキストと問題集各1冊を使用した完全な独学でチャレンジしました。もっと他のものを購入するという手もあったにはあったのですが、勉強開始の時点で本試験まで2ヶ月と、かなり時間もなかったためそのようなかたちになりました。
そしてその分、宅建試験の合格を得るまでにかかった「費用」については通常よりもかなり安く抑えることができたはずです。
もちろん、宅建の試験対策講座は様々な資格スクールが開講しているはずですし、短期間で効率よく合格するために、独学ではなく試験対策講座を受講する受験者も多いはずです。
特にこの試験では、「上位15%程度」に入った受験者が合格を勝ち取るシステムとなっているということがほぼ確実であるため、独学でやっていくよりもプロの指導を受けた方がはるかに効率が良いと思われます。
そしてもし、「宅建試験対策講座を受講する」という選択をした場合には、独学で勉強するのと比べ、合格までにかかる費用は跳ね上がります。ここを気にして、せっかく人よりも勉強できる時間があるのに「講座」を選択肢に入れていない、という受験者の方も居られるかもしれません。
では、一般的に宅建試験に合格するまでにはどの程度の費用が必要になるのか?「独学」で受験する場合と、「試験対策講座」を用いる場合に分けて見ていくことにします。
Contents
独学での宅建受験は厳しいが低コスト
まず、宅建試験を完全に独学で受験する場合の費用について確認していこうと思います。先程も少し触れたように、宅建試験のように「相対評価」で合否が決まってくると言えそうな試験に関しては、やはり試験他愛策講座を受講した方が有利にはなってくるはずです。
しかし、それでもあまり時間が取れないとか、資金的に余裕がないという場合には、独学で合格を目指していくことになります。
そして、宅建試験の受験において「独学」でやっていくことは、合格までにかかる費用という面において試験対策講座を受講した場合よりも圧倒的に優れています。
実際に、僕が宅建試験の合格までに使用したテキストと問題集各1冊の価格は、「テキスト:2,300円」「問題集:2,200円」の併せて5,500円に消費税がかかりおよそ6,000円といったところでした。

もちろん、勉強期間に余裕がある場合にはそれプラスいくつかの問題集や過去問集を用いて勉強していくことになるのではないかと思います。
それでも、比較的数が出るであろう宅建試験の関連書籍はせいぜい3,000円程度でしょうから、「書籍代」としてはどれだけいっても20,000円を超えるようなことはないのではないかと思います。
そして、もし20,000円分のテキストや問題集を購入したとして、それに受験手数料であるおよそ7,000円を追加したとしても、そこで合格してしまいさえすれば、「書籍+受験手数料」を合計しても27,000円という低コストで済むことになります。
また、宅建試験は人気が高いこともあり、試験会場も多くそれなりに近所で受験できる可能性が高いのではないかと思います。おそらく公共交通機関で往復しても1,000円程度の範囲内に会場があるのではないかと思います。
ということで、とりあえずは「本試験当日の交通費」を1,000円、宅建試験の合格に要する費用に付け足しておきます。これは受験手数料と同様、独学でも試験対策講座を受講しても同じです。新幹線で他県まで出向かなくてはならない試験とはえらい違いですが…
となると、テキストや問題集が(多くて)20,000円、受験手数料がおよそ7,000円、それから交通費が1,000円でその合計金額は28,000円、ということになります。
これにより宅建試験を独学で勉強し、上手いこと一発合格できた場合にかかる費用は「30,000円以下」である、ということになります。
この金額は人によって多少は上下するかもしれませんが、テキストなどの書籍で相当な高級品(そもそもそんなのあるのか知りませんが)を使っていない限りは大きく乖離すると言うことはないはずです。
宅建試験は人気も高く、試験対策講座もかなりの数が開講されているようです。しかし、完全に独学で勉強していった場合には、(厳しくはありますが)非常に少ない費用で合格を狙えるものであるということがわかります。
講座を受講すればかなり有利となるはずだが…
次に、宅建試験を受験するにあたり「試験対策講座」を受講した場合にかかるコ費用についてみていきたいと思います。
試験対策講座を取ってプロの指導を受けるという場合には、そこで使うテキスト以外のものを購入して、別途自分で勉強を進めていくという余裕がある受験者の方はそうそう居られないはずです。
よって、「講座組」が宅建試験に合格するまでに必要とする費用は、その大半が「講座の受講料」ということになってくるはずです。
もし、通信講座ではなく通学講座であったり、通信でも一定回数のスクーリングがあるなどという場合には、その分の交通費等も必要になってくるはずですが、ここではその費用については無視しておくことにします。
各資格スクールの受講料比較
では、「講座組」が宅建に合格するために必要となる費用の大部分を占めるはずである「受講料」、これは初学者や経験者など、かなり細分化されてそのステージにより違ってくるはずですが、果たして「一般的」にはどのぐらい必要になるものなのでしょうか?
大手の資格スクールいくつかについて、初学者として宅建試験対策講座を受講する場合の受講料を確認してみました↓
- TAC(宅建士)「総合本科生SPlus(初学者向け)」:192,000円
- 日建学院「宅建本科コース」:(一般)200,000円(学生)100,000円
- LEC「パーフェクト合格フルコース(WEB)」:124,200円(税込)
- 大原「完全合格週2コース(web)」:134,000円
- ユーキャン「宅地建物取引士講座」:63,000円(一括)
こんなところでしょうか?、他にもいろいろとあるはずですが、総じて「受講料がいくらなのか?」ということが非常にわかり辛く、もしかしたら資料請求しないとダメなんじゃないか、というようなところもありました。
まぁ、資格を取りたかったら費用がどうこうなんて言ってんじゃないよ!ってことなのかもしれませんが、「そこが知りたい」のにどこに記載があるのかわからないのは非常に不快です。
結構なお値段だが確実に合格したいのであれば必要経費ととるべき
それはともかく、どうも宅建試験を「試験対策講座の受講」という方法で受験する場合には、高くて20万円、最も安い(今調べて出てきたなかで)ユーキャンでも6万円というコストがかかるということがわかりました。
これに加えて先程独学で受験する際にもあった「宅建試験の受験手数料」と「本試験当日の交通費」は当然に必要となってきます。
となると、「試験対策講座を受講」して宅建試験にチャレンジするという場合にかかる費用は「およそ7万円~20万円以上」ということになってきます。これは独学で受験した場合と比べると「2倍~7倍前後」の費用がかかるということです。
ただ、当然独学と比べて試験そのものの合格率は格段に高くなるでしょうし、勉強する「期間」が短くて済むというメリットがあります。

その点を考慮した場合、宅建試験に挑むには無理に独学でいくよりも「時間・資金が許すのであれば」試験対策講座を受講し、専門家の指導を受けて確実に合格を狙う方が無難であるはずです。
もちろん、突然忙しくなったとかいろいろな理由で試験対策をリタイアしてしまう場合もあるはずです。しかし、そのような事態に陥らず、試験対策講座の全てのカリキュラムを終えたのであれば、宅建試験の合格可能性は相当に高まってくるでしょう。
格安通信講座を利用するという選択肢もある
もうひとつ、宅建試験対策講座を利用するほどの時間的(または資金的)な余裕はないものの、独学で合格できるかどうかはちょっと怪しい、と感じている受験者の方は、普段のテキスト等に加えて「格安のオンライン資格スクール」を利用するという手段検討すべきだと思います。
比較的難易度が高いとされる宅建試験であっても、最近では格安で月額利用が可能な通信講座が出てきています。僕自身、現在は行政書士試験の対策として利用している最中ですのでその効果はまだ未知数ですが、テキスト1冊買うのよりも易い月謝は魅力的です。
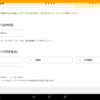
例えば、僕が現時点で登録している「オンスク.JP」では、安い方の月謝として「980円/月」のコースがあります(WEB版)。
もし、宅建試験に合格するために「半年」勉強するとして、先程の独学で合格するために必要となる費用である「およそ30,000円弱」に加えて、「980円×6ヶ月」で「およそ6,000円」を追加すればそれなりの勉強ができます。
また、格安であるせいなのかはわかりませんが、1回あたりの講義時間が非常に短く、「ちょっと時間がある」ぐらいのタイミングでも、スマホを使って勉強を進めることができます。
模試などを受ける場合には+αの費用が
ここまで、「独学」と「試験対策講座の受講」、それぞれの場合で宅建試験に合格するために必要となる費用について確認してきましたが、これに加えて「統一模試」的なものを受験し、本試験前に実力を試す場合には追加的な費用が発生することになります。
おそらく、資格スクールが実施する模試などはそこまで検定料が高くはないはずです。よって都会の方に住んでいるというのであれば特に問題はないのかもしれませんが、東京や大阪などといった、資格スクールが「宅建統一模試」的なものの実施をする地域までの交通費も当然に必要となってきます。
この「宅建模試」を受験するかどうかはその人次第のところもあると思いますし、僕も受験はしませんでした。そもそもそんなに余裕を持って勉強を進めていたわけではありませんが…
また、試験対策講座を受講する場合には、それ自体がセットになっており、追加の費用がかかることなく受験することが可能なものもあるようです。
また、宅建試験を独学で受験する予定であったり、模試のついていない講座を受講している場合であっても、可能であれば受けておいた方が良いのではないかと思います。
そこで何か自分の弱点が見つかるかもしれませんし、本試験の雰囲気に慣れるという効果も期待できそうであるためです。
一発で受からなければ当然費用は嵩む、計画的かつ効率のよい勉強をするべき
最後になりますが、どれだけの費用を試験対策に充てたかに関わらず、宅建試験に不合格ということになってしまった場合には、さらに翌年分の試験対策や受験手数料にお金がかかってくるということを、ここで改めていうほどのことではないかもしれませんが、一応確認しておきます。
もし、試験の結果が不合格であったとしても、そこまでに勉強した知識は身についている状態なわけですから、すぐに試験対策を再開すれば「振り出しに戻る」などということはありません。
しかし、それでも翌年度、新しいテキストを購入したり、もう一度試験対As区講座を受講したりということをすれば、前年度と同程度の費用がかかってしまう可能性もあります。
それを避けるためにも、せっかく勉強するのであれば計画的に、効率の良い勉強をするように心がけるべきでしょう。
僕も宅建試験を受験した際には「権利関係」の難しさに戸惑い、結果として勉強の配分を間違え、合格することはできたとはいっても「ギリギリ」という結果になりました。
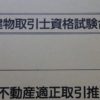
また、試験対策を開始したのが8月の頭と、期間的にもかなり無理のある計画でした。正直、宅建の前にFP2級の試験を受けたことによる予備知識がなかったら合格することは不可能だったでしょう。
これから宅建試験を受験する方々は、十分に勉強時間があるのであればですが、上記「独学なら3万円程度、講座を受講するなら7万円から21万円程度」という費用の中に収まることができるよう、一発合格を目指して勉強を進めていくべきだと思います。
まとめ
今回は「宅建試験の合格までに必要となる費用」について確認してきました。
独学で受験するのか?それとも試験対策講座を受講するのかによってかなりの開きはありますが、そこは受験者本人がどちらで行くべきなのかを判断して決めなくてはなりません。
宅建試験は相対評価で合否が決まる試験であるといえそうなので、もちろん講座を受講して一気に合格ラインを突破した方が有利ではあると思います。
しかし、「受講にはどのぐらいの費用がかかるのか?」ということを考えた場合、特に大学生など、資金的に余裕が無い場合にはかなり難しいはずです。
一方、独学で合格を狙っていく場合にはかなり低コストで宅建試験にチャレンジすることができますが、正直厳しいことは厳しいです…
そのあたりもいろいろと考え、ネットなどを駆使して様々な情報を集めたうえで、自分に合ったスタイルで受験していくことをお勧めします。