8月に実施される税理士試験 簿記論の試験対策として、昨年の「55点」という点数から少しでも成長すべく、この間購入した「堀川の簿記論 個別論点合格レベル100チャレ」を進めています。
この問題集では「個別問題:25点×2」「総合問題50点」の合計100点満点となっている簿記論の試験のうち、「個別問題」に対応するためのもので、”普通の問題集”よりもかなり難易度の高い、割りと複雑な問題が100問収録されています。
で、そのような難易度の高い「本試験レベル」の問題ばかりの当該問題集には結構苦労させられているんですが、今回はそのような問題集を実際にやってみて、1周するかどうかのところで気付いたことなどを記載していこうと思います。
Contents
難しい問題にも少しづつ慣れてきた
今やっている簿記論の問題集「堀川の簿記論 個別論点合格レベル100チャレ」の効果もあってか、本試験で出題されるような複雑な問題文にも少しづつですが慣れてきたように思えます。
昨年の試験対策では、それまでやっていた一般的な問題集、つまり「それぞれの論点について”覚える”」ためのものと、実際に税理士試験の簿記論で出題されるような「本試験レベル」の問題との違いに対応できず、かなり苦労させられました。
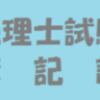
また、そこから続けて過去問を解答してみたものの、やはり同じように問題の内容が難しく、正直言って全く手が付けられないような問題も数多く存在しました。
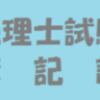
しかし、今回は早いうちにそういった比較的難易度の高い問題に挑戦しており、かつ、それらの問題も結構な数こなしているため、2019年の本試験では全く解答できないようなものは昨年と比べて減ってくるはずです。
とはいえ、税理士試験は簿記論に限らず「解答時間が足りない」というのがどうしても問題になってくるはずです。
「問題自体」に慣れたからといって、現時点ではそれら「本試験レベル」の問題を素早く解答できるわけではないため、これから先、もっと練習を重ね、考えなくても自然と答えが出てくるぐらいにはなっておかないと、といったところです。
電卓の打ちミス・転記ミスが目立つ…
ここまで問題集の解答を続けてきて、2019年の簿記論の本試験で得点を伸ばすことができるかどうかに関して重要な問題が生じてきました。
それは、電卓の打ち間違いや転記のミスが非常に多くなっているということです。
これに関してはもともとかなり多い方なんですが、練習問題をこなしているうちに、少しづつ「最後まで解ける問題」が多くなってきたこともあり、その分何らかのミスが生じることも増えています。
このあたり、ここから先しっかりと修正していく必要があり、また、現在使っている電卓は手の大きさにあっていないようなかなり小さなものであるため、昨年計画しておきながらスルーしてしまった「電卓の買換え」も再度検討していく必要がありそうです。

範囲によってできるできないの差が大きい
さて、ここからが本題になります。昨年の合格発表後から簿記論の試験対策を再開し、今年の税理士試験に向けて「ひたすら練習問題を解く」という方法を実践しています。
そして、新たに「堀川の簿記論~」も追加してさらに試験対策のペースを上げたこともあってか、「できる範囲」と「できない範囲」の差がかなり大きくなってしまったように感じます。
これまで受験した他の資格試験でもそうでしたが、「何度やっても全く覚えられない」とか「覚えたつもりでも問題になると解けない」というような範囲が必ず出てきました。
簿記論でもやはり、そういった範囲や論点がいくつか現れ、そういったものについては基本的な問題ですら「これなんだっけ…?」となってしまうことがよくあります。
特に、「本試験レベル」の問題集では、デリバティブ取引などのマイナーな論点や、委託販売ではなく”受託”販売など、一般的な問題集では扱いの無いような問題についても普通に収録されています。
ただでさえ”苦手”な範囲・論点の中で、さらに普段余り目にしないようなちょっと薄めの問題が出題されると、昨年の試験対策では多くの範囲でそうであったように、「全く解答できない」状態になってしまうことがあります。
しかも、それらは一旦解答・解説に目を通してからもう一度解きなおしたとしても、また「何をやったら良いのか」すらもわからなくなってしまいます。つまり、一向に前に進むことができません。
そしてその間も、他の「普通にできる」範囲・論点については練習を重ね、解答に要する時間も着実に短くなり、変な間違いや勘違いなども減ってきていますから、そういったものとの差がかなり広がってしまっているように思えます。
このまま本試験まで行ってしまった場合、得意な範囲が出題されればかなり得点できるものの、逆に苦手な範囲で複雑な問題が出題された場合には、その部分を丸ごと失点してしまうことになりかねません。
そうなると、実際に試験問題を見るその瞬間まで、どれだけ勉強をしていったところで全く自信が持てず、それゆえ試験対策の時間を簿記論ばかりに充てることになってしまい、今年の税理士試験で同時に受験する予定の「財務諸表論」や「酒税法」は、またも手付かずのままになってしまうかもしれません。
それはさすがにまずいですから、これから先、本試験までの間に、どうあっても「苦手な範囲・論点」を全て克服し、それなりの問題までは十分に解答にたどり着けるようにしておく必要がありそうです。
そのための具体的な方法はこれからもっとよく考える必要がありますが、とりあえずは苦手な範囲を他よりも意識して、ちょっと多目に問題をやっていくようにします。
特に苦手な範囲は2つ
では、どの範囲が”苦手”なのか?これは昨年の試験対策でもかなり感じていたことなんですが、もっとも出来が悪いのは「特殊商品販売」と「本支店会計」です。
もちろん、税理士試験に限らず「簿記」の勉強をしている方は、この2つの範囲が苦手だということが多いのかもしれません。
特殊商品販売に関しては「手元商品区分法」とかなんとか、いろいろな技がありすぎてよくわかりませんし、本支店会計はとにかく集計しなくてはならない量が多く、どこかで躓いて解答にたどり着けないことが多くなってしまいます。
そして、全範囲の練習問題をやればやるほど、特殊商品販売・本支店会計と他の範囲との差が開いてきてしまっていますので、この2つについては今後特に注意しておく必要がありそうです。
ミスの多い論点にも注意していきたい
最後に、得意とか苦手とかではなく、単純に電卓や計算のミスが他よりも目立つ論点もかなり気になっています。
先程も少し触れたように、電卓のミスや転記ミスなど、ちょっとした間違いがかなり出やすくなってはいますが、論点、というか一定の問題において、他のものよりもそういったミスが多くなっているように感じます。
特に、期中に何かアクションを起こし、それを月割りで按分するような問題のときに、変な数え間違いや、ちゃんと数えたのに途中で電卓に違う数字を打ち込んでいたなんてことがよくあります。
また、利息の計算などで小数点以下の細かい数字を打ち込むときや、その利率等をメモ書きしたときに、違う数字を書き込んでしまったりといったことも多いように感じています。
そういったタイプの問題が出題されるような論点では、やはりその分ミスが増えていくことになります。特に苦手としている範囲・論点ではなく、問題自体が簡単な内容であっても、つまらないことで失点してしまう可能性は十分にあるわけですから、そうならないための対策を考えなくてはなりません。
そこで、ここから先は「ちょっとしたミス」の発生を確認した際には、それがどこの範囲・論点で生じたのかをメモしておき、「ミスの多くなっている箇所」を正確に洗い出していくことにします。
そうすれば、これから先の試験対策でも、そして本試験の解答中にも、「ここはミスが多いところだから気をつけよう」と意識できることになり、結果としてうっかりの失点を防ぐことができるようになるのではないかと思います。
まとめ
今回は2019年の税理士試験 簿記論の試験対策をしていて、「本試験レベル」の問題集をそろそろ一周するかどうかの現時点でわかったこと、気になることなどを記載してきました。
今の時点では、最も大きな問題として「範囲・論点ごとの解答力に差が出過ぎている」というものが挙げられます。これをどう解消していくのか?ひたすら問題を解く以外にも何か解決策を考える必要がありそうです。
また、それ以外にも電卓や転記のミスが目立ち、また、論点によってそういった間違いが多いところがありそうな感じです。これに関しても同時に対応策を考えなくてはなりません。
税理士試験の本試験はまだまだ先ですが、ここで気を抜かず、今年の試験で「せめて簿記論だけは」何とかできるよう、試験対策を続けていきたいと思います。